ふるさと納税に興味はあるけれど、「仕組みが複雑」「損をしたらどうしよう」と不安に感じていませんか?
この制度は、仕組みさえ理解すれば、豪華な返礼品を受け取りながら、税金が安くなるというメリットを享受できる魅力的な制度です。
この記事では、初心者が抱きがちな3つの大きな疑問に、分かりやすくお答えします。
疑問1:結局、私にとってのメリットは何?
ふるさと納税の最大の魅力は、「地域応援」と「家計の節約」を両立できる点にあります。
メリットA:実質2,000円で特産品が手に入る
- 仕組み: あなたが寄附した金額のうち、2,000円を除く全額が、翌年の税金から差し引かれます(控除)。
- 結果: どの自治体に、いくら寄附しても、最終的な自己負担はたった2,000円です。この2,000円の負担で、寄附額に応じた地域の特産品(お肉、お米、海産物など)を受け取ることができます。
メリットB:地域貢献ができる
寄附金の使い道は、教育、環境、子育て支援など、自治体が自由に設定しています。「この地域を応援したい」という思いを、具体的な支援という形で実現できます。
疑問2:いくらまで寄附して大丈夫?「上限額」のルールとは?
ふるさと納税で損をしないための最重要ルールが「控除上限額」です。この上限額を超えて寄附すると、超過分は税金から戻らず、全額自己負担になってしまいます。
ルール1:年収が高いほど上限額も高くなる
控除上限額は、あなたが納めている税金の額に応じて決まります。
- 年収が基準: 手取りではなく、源泉徴収前の「額面(総支給額)」が高ければ高いほど、上限額も高くなります。
ルール2:家族構成で上限額が変わる
- 扶養家族がいる場合: 控除がすでに適用されているため、上限額は低くなります。
- 独身または共働きの場合: 上限額は比較的に高くなります。
初心者の行動:必ずシミュレーションしよう
上限額は複雑な計算で決まるため、自己判断は危険です。
まずは、ふるさと納税サイトにある無料の「上限額シミュレーション」を利用し、年収と家族構成を入力して、おおよその目安額を知ることから始めましょう。シミュレーションで出た金額を参考に、余裕をもって寄附するのが賢明です。
疑問3:手続きは面倒?「5団体」で何が変わる?
ふるさと納税は、寄附した後に必ず税金控除の手続きが必要です。この手続きが「簡単になるか、手間がかかるか」は、寄附先の自治体の数で決まります。
A. 5団体以内なら【ワンストップ特例制度】で簡単!
- 対象: 確定申告の必要がない会社員などで、寄附先が年間5団体以内の人。
- 手続き: 確定申告が不要になり、寄附先からもらう書類を郵送するだけ。
- 税金: 翌年の住民税が安くなる形で控除されます。
B. 6団体以上なら【確定申告】が必須!
- 対象: 寄附先が年間6団体以上になった人、またはもともと確定申告が必要な人。
- 手続き: 翌年3月までに、寄附先すべてからもらった「寄附金受領証明書」を添えて、税務署に確定申告を行います。
- 税金: 所得税から一部が現金で戻り(還付)、残りが住民税から控除されます。
初心者へのアドバイス
「手続きが面倒そう」と感じる方は、まずは寄附先を「5団体以内」に絞り、ワンストップ特例制度を利用するのが、ふるさと納税を最も手軽に始める方法です。
不特定多数の自治体から探せる「Amazonふるさと納税」
ふるさと納税は、Amazonのサイト内でも手続きが可能です。Amazonならではの使いやすさで、全国の自治体の情報を比較しながら寄附先を選べます。
Amazonふるさと納税の特設ページでは、多様なカテゴリから魅力的な寄附先と、そのお礼の品を比較検討できます。

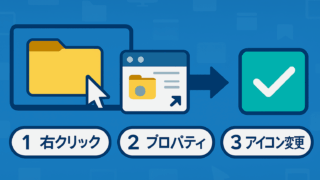
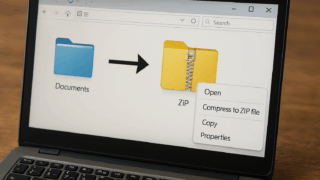
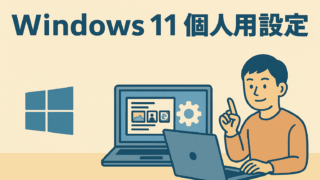

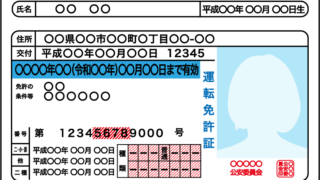

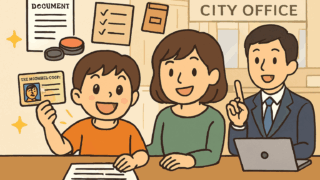
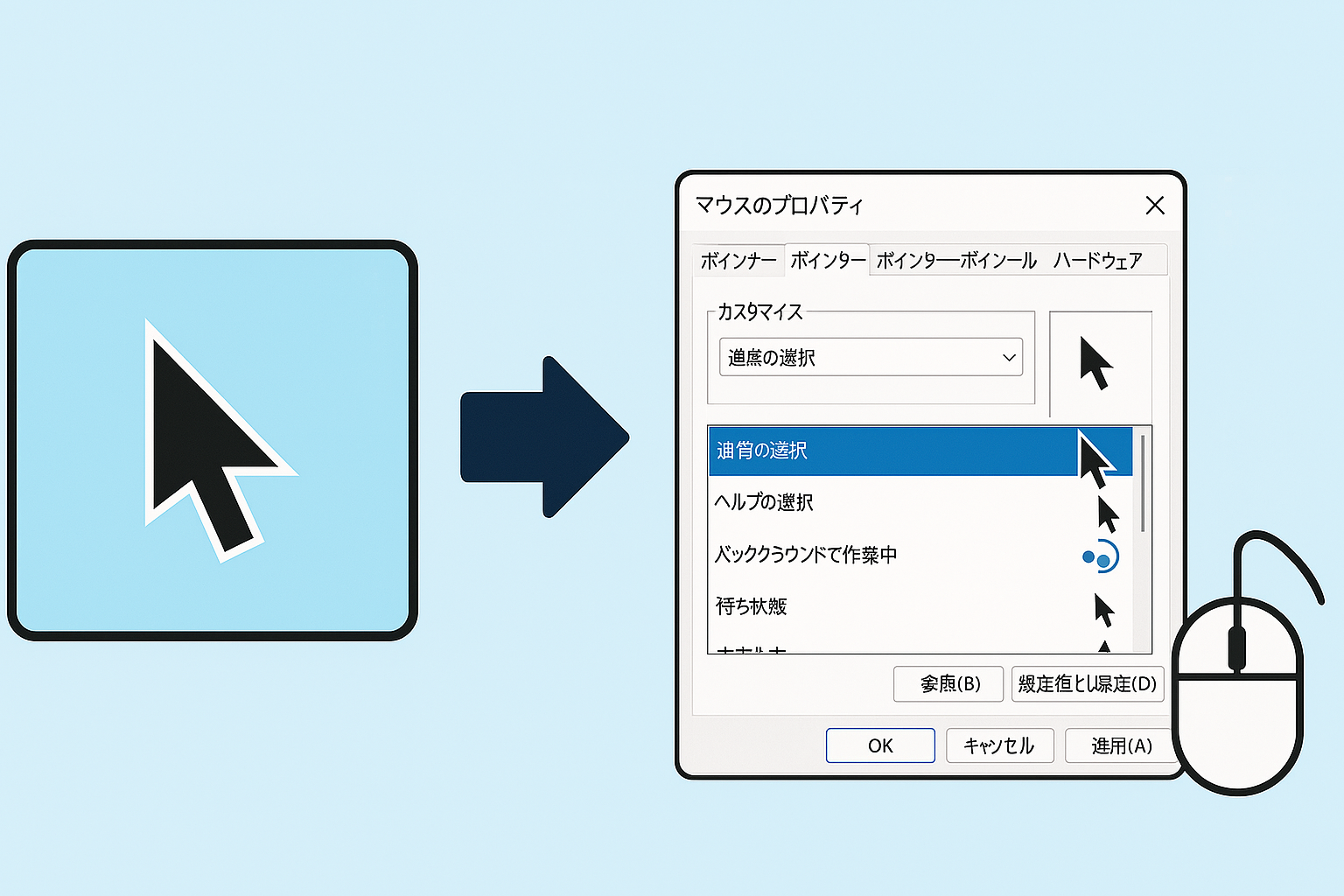
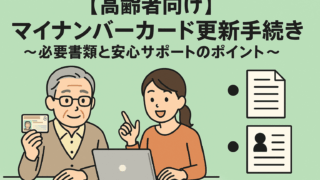

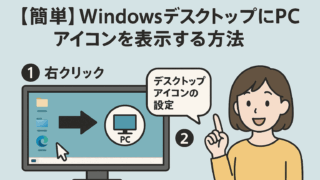





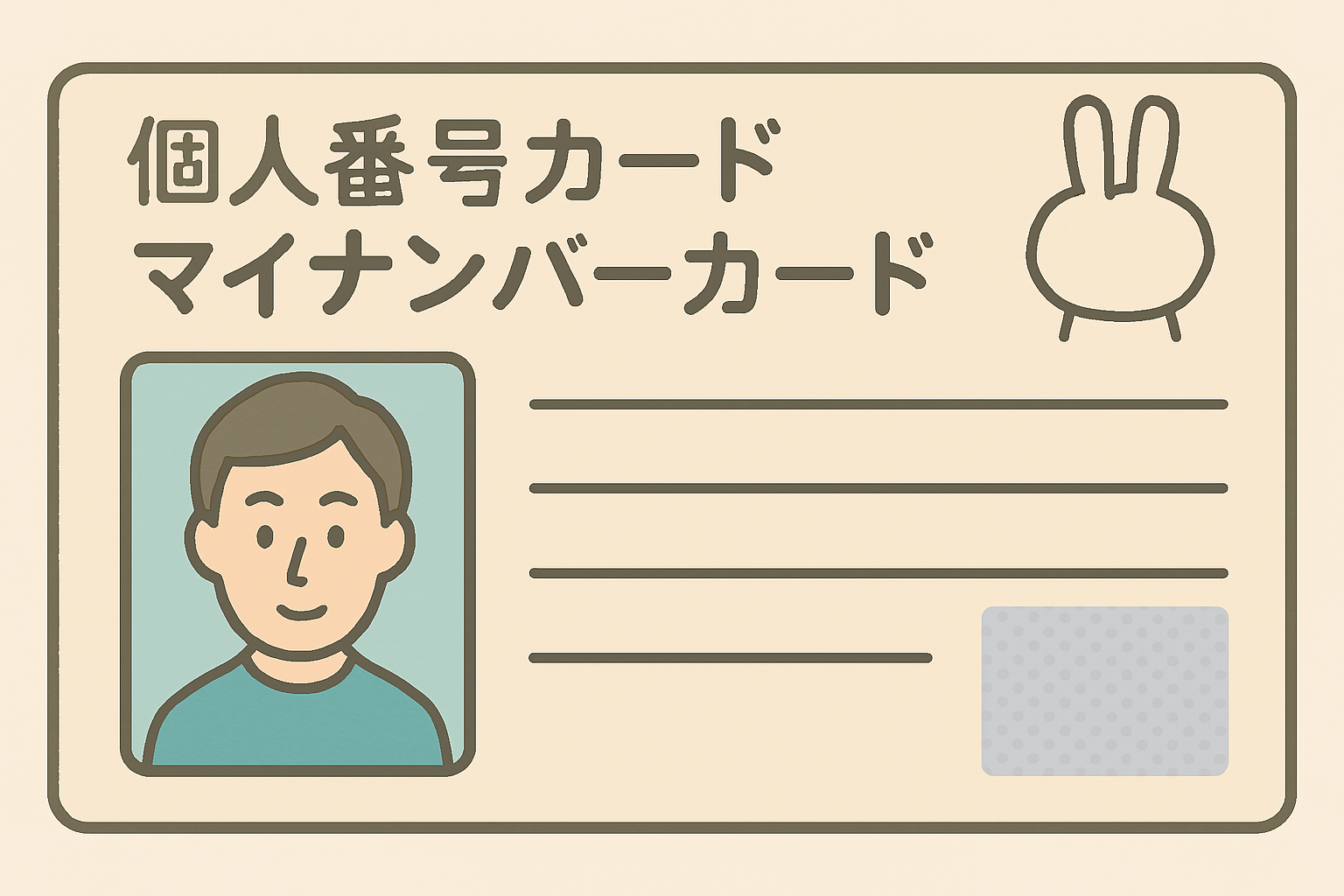

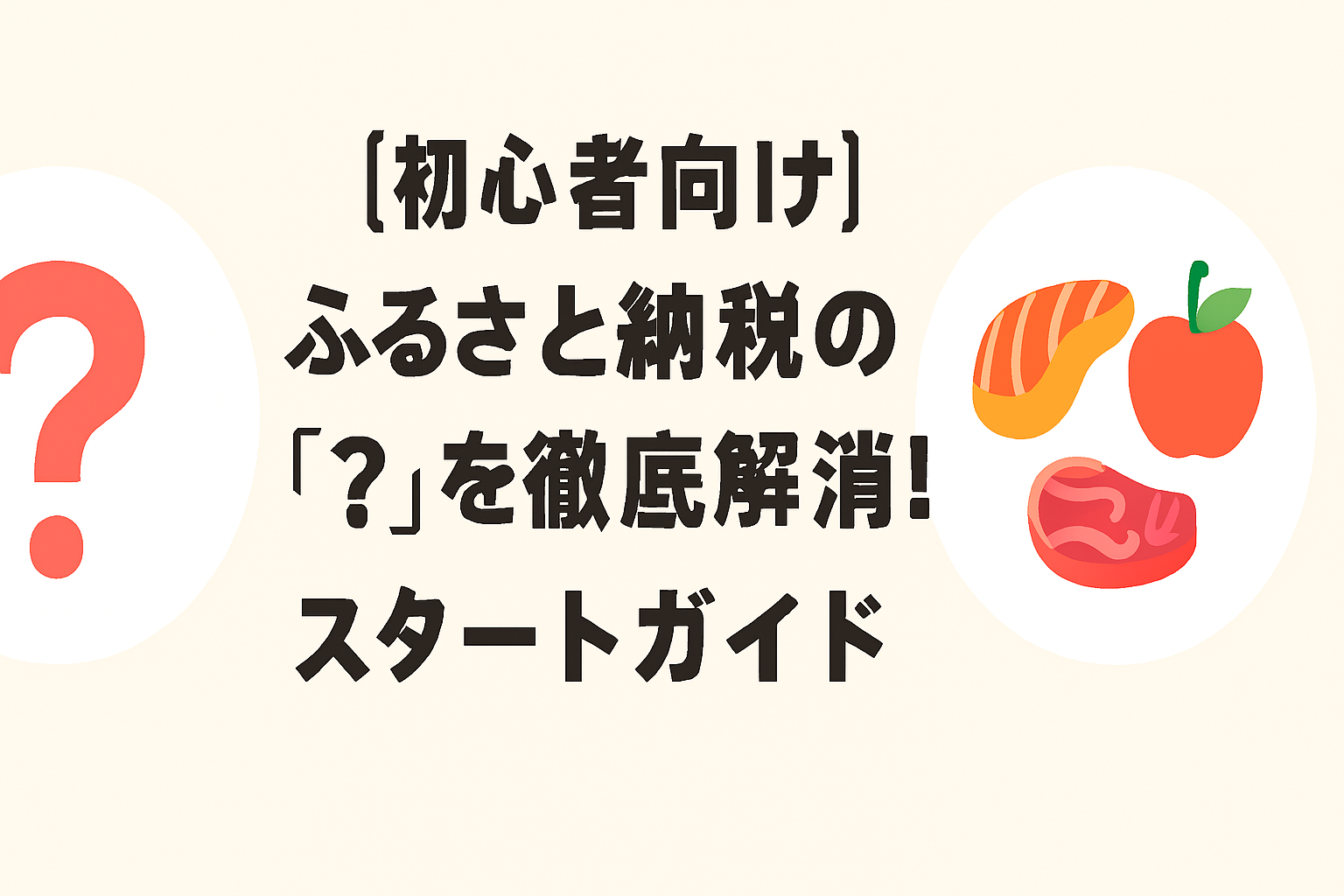
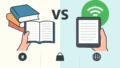

コメント